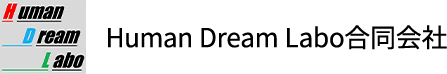#228 自分を責める癖:内なる声を味方に変える方法
BLOG
メンタル症状・不安/抑うつ
初めての方
「またうまくいかなかった……」 「どうして私はいつもこうなんだろう」
何かあるたびに、自分を責めてしまう。 そんな“心のクセ”に、あなたも思い当たることはありませんか?
今回は、「内なる批判の声」とどう付き合っていくか、そしてどうすればその声を“味方”に変えていけるか。
心理学と脳科学、そして具体的な実践を通して、あなたの心を少しずつやわらげていく方法をお伝えします。
◾️相談者事例(Bさんのエピソード)
Bさん(30代女性・経理)は、上司に「確認が足りなかったね」と指摘された瞬間、涙があふれそうになりました。
「またミスした……やっぱり私はダメな人間だ」
そう思うと、胸の奥がぎゅっと縮こまり、なかなか仕事に戻れなかったそうです。
実はその日、他の作業で多くの資料を抱えていたBさん。
でも、自分に厳しい目を向けてしまうクセが、「状況」よりも「自分の人格」を責める思考に直結していたのです。
◾️心理学解説:自動思考とスキーマ
「私はダメだ」「きっと嫌われた」
このような考えは、“自動思考”と呼ばれるもので、過去の経験から自動的に浮かぶクセのようなものです。
そして、その背景には「失敗してはいけない」「完璧でなければ価値がない」といった“スキーマ(思い込みのルール)”が隠れていることがあります。
Bさんのように真面目で責任感の強い人ほど、自分への評価が厳しくなりやすく、自動思考のスピードも速くなりがちです。
◾️脳科学解説:内なる声と扁桃体・海馬の働き
自分を責めるとき、脳では「扁桃体(へんとうたい)」が強く反応し、危険や不安に対する“防御反応”が起きます。
このとき、過去の似た経験を記憶している「海馬(かいば)」が活性化し、
「またあのときみたいに怒られるかも」といった“予測”が働いてしまいます。
その結果、まだ起きてもいない未来まで不安になり、責める声がさらに大きくなるのです。
だからこそ、自分を責めそうになったときこそ、脳を落ち着けるセルフケアが役立ちます。
◾️声紋分析から見る傾向:Bさんの声の特徴
Bさんの声を分析すると、ブルー〜ネイビー(視感覚・客観視)に強い波形がありました。
この傾向は、常に「こうあるべき」「こう見られているはず」といった“理想の姿”と現実を比較しやすいタイプに見られます。
また、判断基準は「社会軸(マゼンタ)」が強く、「みんなの期待に応えたい」「ちゃんとしていたい」という思いが人一倍強いことがわかりました。
その結果、少しの失敗でも「自分が足りなかった」と自分を責める思考回路ができてしまっていたのです。
◾️実践例とヒント:内なる声を書き換える
Bさんのような「自分責め」タイプが、内なる声を味方に変えるには、まず“気づくこと”から始まります。
🔹ステップ①:責める言葉をそのまま書く 「なんでできなかったの?」「やっぱり私はダメだ」
🔹ステップ②:その背景にある気持ちを探る 「本当は、認められたかった」「がっかりされたのが怖かった」
🔹ステップ③:やさしい声で書き換える 「うまくいかなかったけど、チャレンジしたことは事実だよ」 「今回のことで、次はこうしようと気づけたね」
このように、感情に寄り添いながら“声のトーン”を変えていくと、心の内側から落ち着きが戻ってきます。
◾️セルフケアの提案
U-LaLa446 呼吸法(落ち着きの呼吸)
やり方:背筋を伸ばし、鼻から4秒吸う → 4秒止める → 口から6秒吐くを5分繰り返す。
効果:副交感神経を高め、扁桃体の過活動を鎮め、不安やストレスを落ち着かせる。
備考:丹羽真一, 2019, 福島県立医科大学/Nivethitha et al., 2016, J Clin Diagn Res
感情ラベリング
やり方:今の気持ちを単語で書き出す(例:「焦っている」「悲しい」「悔しい」など)。
効果:前頭前野が活性化し、感情が整理され、自動思考に飲まれにくくなる。
備考:Lieberman et al., 2007, Psychological Science
U-LaLa “小さな成功”メモ(3つのよかったこと日記)
やり方:寝る前にその日「できたこと・よかったこと」を3つ書き、その理由をひと言添える。
効果:自己効力感が育ち、「できなかったこと」よりも「できたこと」に意識が向く。
備考:島井哲志, 2010, 関西学院大学/Seligman et al., 2005, American Psychologist
◾️クライエントさんの声
「“私はダメ”のループから、ようやく抜け出せました」
「ノートに書いてみると、自分が思っていたより頑張っていたことに気づけました」
「最近は、失敗しても“次はこうしよう”と思えるようになっています」
◾️カウンセラー視点
Bさんは、はじめは「責める声があるのは悪いこと」だと感じていました。
でも、その声の奥には「よくなりたい」「認められたい」という健気な気持ちがあると気づいたことで、
少しずつ“味方の声”として受け取れるようになっていきました。
◾️まとめ
自分を責める癖は、過去の経験や思い込みからくる“自動反応”です。
けれど、意識して言葉を選び直すことで、心のパターンは書き換えることができます。
まずは、「自分にやさしい声をかける」ことから始めてみませんか?
それが、内なる声を味方にする第一歩です。
◾️U-LaLaカウンセリング案内
・U-LaLa(うらら)では、心理学・脳科学・声紋分析を組み合わせたやさしいカウンセリングを提供しています。
・2025年8月より一般社団法人 日本認知・行動療法学会(CBT学会)会員として活動を開始。最新エビデンスに基づく認知行動療法(CBT)を中心とした支援体制を強化し、“根本改善”を加速します。
・6秒の声から、あなたの“判断基準”と“行動基準”がわかります。
・オンライン・電話でも対応可能です。
・初回は無料でご相談いただけます。お気軽にお問い合わせください。
▶ ご予約・詳細はこちら https://www.human-dream-labo-kokoro.com/
#自分を責める癖 #内なる声 #自動思考 #スキーマ #扁桃体 #海馬 #感情ラベリング #自己効力感 #完璧主義 #自己否定 #視感覚優位 #社会軸 #U-LaLa #心理カウンセリング #脳科学 #声紋分析 #ストレスケア #認知行動療法 #小さな成功 #呼吸法 #心のクセを整える #HSP気質 #自分にやさしく #カウンセリングで安心 #気持ちの切り替え